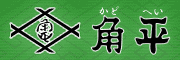
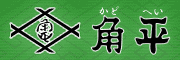


『「つけ天」元祖を自負』
天ぷらも、そばもおいしく生かすために、冷たいそばを温かい汁で食べる「つけ天」。開港150周年を迎えた横浜には「日本初」が多いなか、日本そば店角平(かどへい)(同市西区平沼1丁目)は、このつけ天の元祖を自負する。つけ天について調べ、食べてみた。
◆天ざるの本家も知らぬ味
もとはカツ屋だった角平は、前おかみの藤江婦美子さんが1950(昭和25)年、そば屋に衣替えした。
娘で今のおかみ、壽子さんによると、つけ天は最初、まかないだった。裏メニューになり、60年ごろまでに看板メニューになった。
つけ天は、どれほど知られているのだろうか。
全国麺(めん)類生活衛生同業組合連合会(東京都)の担当者は「分からない」。北海道から兵庫の13組合に尋ねても、神奈川以外は「聞いたことがない」と口をそろえる。
「『天ざる』を『温かい汁』でという注文に応じる店もある」(北海道)。静岡県の15代続くそば店主(72)は「似たものでは天ぬきという、天ぷらそばのそば抜き。メニューにないが、酒のさかなに注文する人もいます」。
東京都の組合は、中央区日本橋の室町砂場を紹介してくれた。1869(明治2)年創業のしにせは「天もりと天ざるはここが発祥」という。
室町砂場の店主村松毅さん(40)によると、天ざるができたのは戦後の50年ごろ。「天ぷらそばを夏の暑い時期にも食べやすくと、そばを冷たいせいろにしたのが始まり」と説明する。
しかし、つけ天を知らないといい、違いを「うちでは天ぷらはエビではなくかき揚げです」と村松さん。
県の組合理事長でJR関内駅近くのしにせそば店「利久庵」の出川修治さん(70)は「そばと天ぷらと温かい汁のアンサンブルは簡単なようで他を寄せ付けない。つけ天といえば角平と育て上げたのは大したもの」と称賛する。
◆ぷりぷり熱々 はしが止まらず
平日の午後7時過ぎ、角平に行ってみた。多くの客を迎え送った玄関の引き戸は、開閉で枠木が丸みを帯び、歴史をしのばせる。昭和の雰囲気は、がたごとと店の横を通る京浜急行の音や、目配りの利いた店員の制服にも漂う。
そばは、北海道十勝産を使い、職人が手でこね、足で踏む。汁が一番大切で、おかみの壽子さんが毎朝味を確かめている。
つけ天は1,150円。会社員が毎日食べるには少々高い。エビなしでホウレン草となると、揚げ玉が入った840円のものは、健康志向の女性に人気があるという。
客の約9割はつけ天を頼む。ほかを注文しようと思って来ても、つけ天にしてしまう人が多いという。
つけ天がきた。湯気の上がる汁がわんに入る。わんのふちからしっぽが出ている大きなエビの天ぷらが、汁の中に4分の1ほどが入っている。
汁は濃い口。ボリュームあるそばで、だんだん薄まるからだそうだ。だしとユズのかおりが混じって懐かしい。
天ぷらそばだと、天ぷらは完全に汁につかって、やがて衣とエビが分離する。それがつけ天だと、汁の量と天ぷらの大きさの関係で、一部がつかり、残りは出たまま。
エビ天ぷらをかじる。ぷりぷり、熱々だ。わんに戻すと、今まで汁に触れてなかった部分がつかる。
そばはこしがあり、たっぷり汁に浸す。つるつると、のどごしがいい。またエビをかじると、汁につかりすぎていない。そばの量もたっぷり、気取りなくうれしい。
壽子さんは「自分で見る範囲の商売なので、支店は出しません。お客の『おかわり』の声と、高校生の孫が『継ぐ』と言ってくれたのが励みです」。
◆筆者の横顔
82年に朝日新聞社に入社。現在、横浜市と川崎市の北部をエリアとする田園都市支局長。神奈川の食に関する話題を集めた企画「ヨシ食うぞう」を執筆中。55歳。
朝日新聞(2009年03月04日)「渡辺嘉三のヨシ食うぞう!!」より

このたび携帯サイトを開設しました!
携帯からでも角平の情報をご覧いただけます。
ぜひアクセスしてみてください。